種の話 その2
F1品種はいいことづくめですが、F1品種を効率よく、それこそ商業ベースにのせるほどに大量生産するためには、自然に育てていたのではとても足りません。そりゃもう、日本だけでも年間どれだけの野菜を食べているのかと思うと、気の遠くなるほどの種がいるわけです。もちろん、種だけでなく育ててて実を採って流通させて…と気の遠くなるほどの数がいるわけですね。
そこで、ちょっと専門的になってきますが、植物が持っている「自家不和合性」「雄性不稔」といった性質が使われます。
「自家不和合性」は「自分の花の中にある雄では受粉しない」性質のことで、「自家不和合性」を持った植物は、同じ花の中にある雄と雌では受粉しません。
「雄性不稔」は「雌だけの花」です。雄を持たないので、自分の花では受粉できません。
例えば、これらの性質を持った植物同士を隣り合わせで育てると、「自家不和合性」の雄(花粉)は自分の雌(めしべ)とは受粉できず、お隣の「雄性不稔」の雌としか受粉できません。
一方、「雄性不稔」の植物は自分の花粉を持たないので、やはり「自家不和合性」の雄としか受粉しないのです。これにより「雄性不稔」の植物に種ができますが、「まったく違う形質同士を掛け合わせ」たことにより、雑種強勢が働き、いいとこ取りの植物ができるわけです。
これで効率よく、交配した種、つまりF1品種の種ができます。
種苗会社は膨大な種類の様々な野菜を掛け合わせ、実験して、経済的に成り立つ野菜を『開発』しているわけです。こういっちゃなんですが、野菜も今や「開発された製品」なんです。
なんだか話がどんどん専門的になってきたので、その3に続く。(と思う)
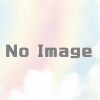



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません